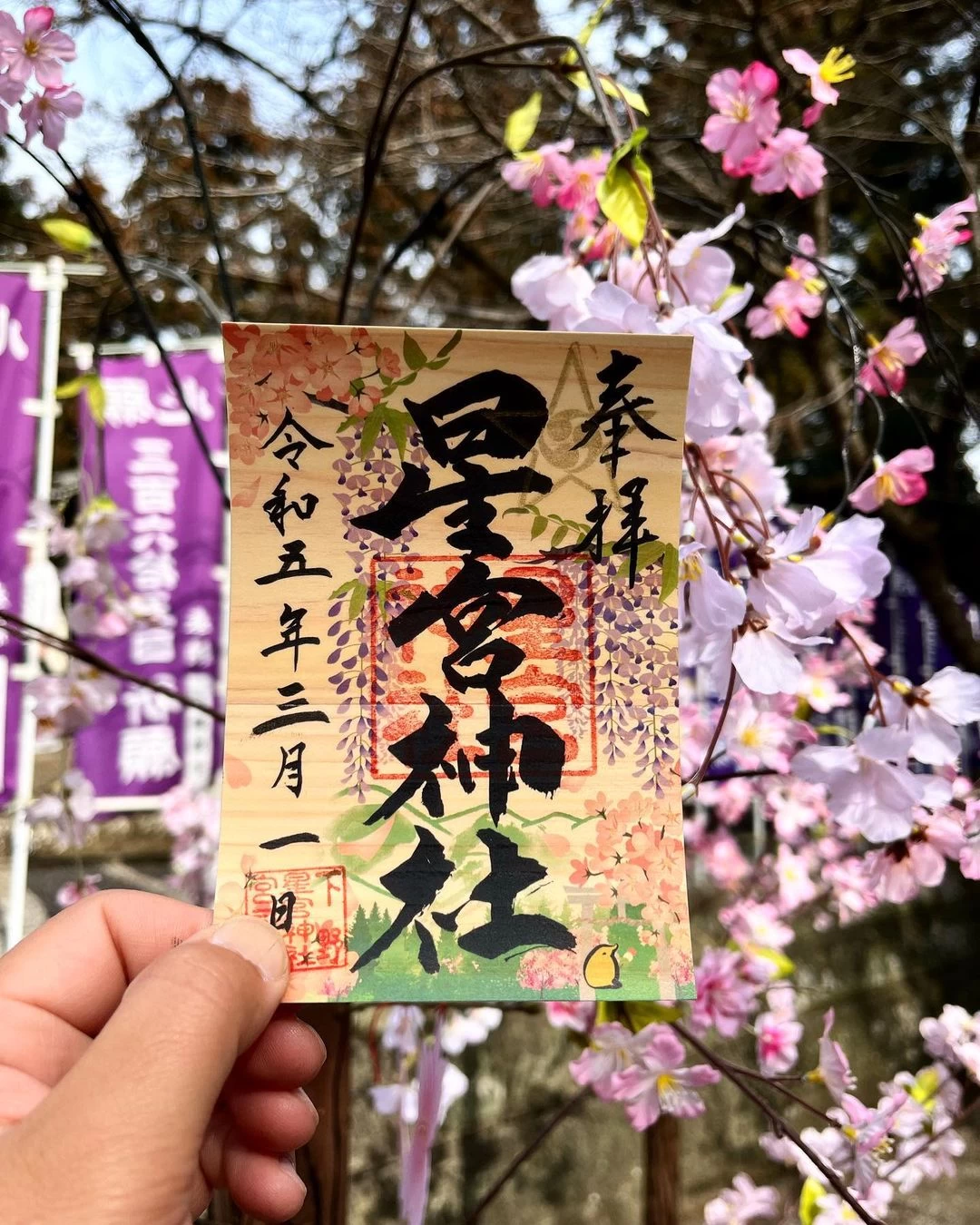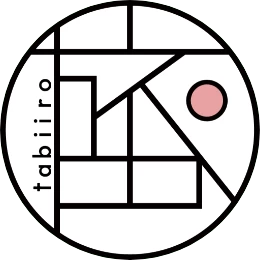Plan No.2172
- 日帰り
栃木・足利で日帰り歴史旅 日本最古の学校や足利氏館跡へ
足利(栃木県)
予算:3,000円〜
・旅行する時期やタイミングにより変動いたします。あくまでも目安ですので、旅行前にご自身でご確認ください。
・料金は1名あたりの参考価格になります。
更新日:2024/01/31
栃木の小京都で足利氏の故郷を巡る
栃木の小京都ともいわれる足利市。日本最古の学校「足利学校」、城跡にして約800年の歴史をもつ古刹「鑁阿寺」。ふたつの史跡を中心に、歴史あふれる町を存分に満喫する日帰り旅をお楽しみください!
こんな旅気分の人におすすめ

足利駅
SPOT1
日本最古の学校
足利学校

足利学校

庫裡(くり:寺院の台所や僧侶が居住する場所)

裏門(内側)

杏壇門(きょうだんもん)

水堀
平安時代初期に創設されたと伝えられる中世の教育機関。室町~戦国時代にかけて、関東における事実上の最高学府として機能した。現在では「教育の原点」「生涯学習の拠点」として親しまれている。

佐藤颯竜のおすすめポイント
- ★ 創建時期については諸説ある「足利学校」。奈良時代の国学の遺制説、平安時代の小野篁(おののたかむら)説、鎌倉時代の足利義兼(よしかね)説などさまざまですが、どれが正しい説であるかは現在も解明されていません。確かなのは、室町時代中期に関東管領の上杉憲実(のりざね)が学校を再興したということ。それから16世紀初頭には生徒3,000人を数え、フランシスコ・ザビエルによって「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学」と世界に紹介されるほどにまでなりました
- ★ 現在の足利学校の姿は、落雷により消失してしまった江戸時代の姿を復元したもの。当時の学生がどのように勉強していたのかを想像しながら、江戸時代にタイムスリップした気分をお楽しみください!

佐藤颯竜のおすすめポイント
- ★ こちらの特徴といえば、在来種のそばの実と、添加物を使わずに昔ながらの製法で打つおそば。在来種とは、古来から日本各地で育ってきた“自然のそばの実”のこと。味が濃く、しっかりした食感です。在来種は栽培が難しく、とても貴重な存在。扱うお店は全国20数カ所しかなく、有名店でもなかなか味わえない珍しいそばなんです
- ★ 江戸時代のそば店は、日本酒を飲む場所でもありました。こちらはそんな伝統文化も提供してくれるお店です。普通では入手困難な銘柄など、ほかでは味わうことのできない日本酒が揃えられ、その数なんと約100種。風味豊かなおそばとともに、希少で美味しい日本酒もぜひお楽しみください
- ★ 個室、大広間、お店全体の貸切利用も可能です。最大人数は約85名、全席禁煙です
SPOT3
建立以来800年余りの古刹
鑁阿寺(ばんなじ/足利氏館跡)

鑁阿寺(ばんなじ/足利氏館跡)

本堂(正面)

楼門(内側)

本堂(遠目)

水堀
約4万平方メートルに及ぶ敷地からなる古刹。足利氏館跡であるため、四方に門を設け、周囲に土塁と堀がめぐらされている。鎌倉時代後期に見られる武士の館の面影が残されていることから、「史跡足利氏宅跡」として国の史跡に指定されており、「日本100名城」にも選出されている。

佐藤颯竜のおすすめポイント
- ★ 足利氏館は、12世紀末頃に足利義兼が築城したとされる源姓足利氏の居城。水掘りと土塁に囲まれた鎌倉時代の武士館の典型であった方形居宅で、在地領主クラスとしては最大級です。今に残る遺構は当時の姿を色濃く残しており、鎌倉時代の武士館の面影に触れられる、とっても貴重な場所です
- ★ 寺院としては、鎌倉時代初期の1197(建久7)年に、源姓足利氏2代目足利義兼が邸宅内に持仏堂を建てたのが始まりとされています。鎌倉~室町時代にかけて、寺院として次第に整備され、室町将軍家、鎌倉公方家などにより、足利氏の氏寺として手厚く庇護されてきました。現在は本堂をはじめ、鐘楼(しょうろう)、一切経堂(きょうどう)が国の重要文化財に指定され、東門、西門、楼門(ろうもん)、多宝塔(たほうとう)、御霊屋(おたまや)、太鼓橋(たいこばし)が栃木県指定建造物に指定されています

佐藤颯竜のおすすめポイント
- ★ もとは米蔵だった建物をリノベーションした店内は、高い天井が開放感を生み出し、木造建築ならではの風情あふれる空間になっています
- ★ ぜひ、スペシャリティコーヒーと手作りスイーツのペアリングをお楽しみください! 美味しいコーヒーと、コーヒーに合うスイーツで「のんびり、ゆったり、ちょっと良い」ひと時を